CG制作を依頼したい!価格相場や失敗しない外注先の選び方について解説

「製品紹介動画にCGを取り入れたいけれど、どこに依頼すればいいのだろう?」
「CGの外注費用はどのくらいかかるのか、相場が分からない…」
CG制作の外注に関して、このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。CGは実写では難しい表現を可能にし、商品やサービスを効果的に伝えるための強力な手段です。
しかし同時に、専門性が高く、依頼先や制作内容によって価格や仕上がりが大きく変わるため、慎重に検討する必要があります。
本記事では、CG制作を外注に依頼する際のメリットや注意点、依頼先の種類、価格相場、コストを抑えるポイントまで、発注前に押さえておきたい情報をまとめました。CGの依頼がしやすくなるように、どんな依頼の仕方をすれば安心できるか確認してみてください。
ちょっと待って!それ、本当にCGでやるべき?
CG制作を検討するときに、まず考えたいのは「この映像表現は本当にCGが必要かどうか」です。
CGで表現すれば自由度の高い映像を作れますが、費用も時間もかかります。そのため、目的次第では他の方法で十分な場合もあります。
たとえば、雨や霧、火花といった効果は、すでに用意されている映像素材を合成するだけで表現できます。市販の素材アセットを使えば、リアルさを保ちながら短時間で仕上げられるので、ゼロからCGを作るより効率的です。
具体例を1つ挙げると、ActionVFXのようなサービスは世の中に多く存在します。
また、最近はAIを使った制作補助も選択肢になっています。背景イラストを生成したり、イメージボードを作ったりする用途なら活用しやすいでしょう。
商用利用の範囲や品質の面ではまだ注意が必要ですが、企画段階でイメージを形にするツールとしては便利です。
つまり、素材の合成やAIをうまく取り入れれば、必ずしもCGに外注しなくても済むケースがあります。
一方で、現実には存在しない映像を作りたい、危険で撮影が難しいシーンを再現したい、製品の内部構造を見せたいなどは、やはりCG制作の依頼が欠かせません。
CGを外注に制作依頼するメリット
CG制作を外部に依頼することで様々なメリットがあります。ここでは代表的な4つのポイントを紹介します。
世界に存在しないものもデジタルで実現
CGを使えば、現実には存在しないものも映像として表現できます。
未来都市や架空のキャラクター、巨大な建造物など、撮影では不可能な対象を自由に描けるのはCGならではの強みです。危険なシーンや大掛かりなセットが必要な状況も、CGなら安全に再現できるため、企画の幅が大きく広がります。
さらに、製品の内部構造や流体のシミュレーションのように、現実では可視化できない情報を分かりやすく伝えられるのも大きな魅力です。
専門技術でハイクオリティな仕上がり
制作会社やフリーランスは、CG制作に特化した技術と経験を持っています。モデリングやアニメーション、ライティングなど、専門性の高い工程を外注することで、自社では再現できないクオリティを実現できます。
映像の完成度が高まれば、視聴者の印象にも直結し、効果的な発信につながります。加えて、プロが持つ表現の引き出しを活かせば、自分たちでは思いつかなかった新しいアイデアを取り入れることもできるでしょう。
伝えたい内容に絞って発信可能
実写映像では不要な背景や細部が映り込むことがありますが、CGなら必要な情報だけを描き出すことができます。
商品の特徴やサービスの仕組みなど、見せたい部分に焦点を当てて映像化できるため、伝えたいメッセージをより明確に届けられます。
特に複雑な技術や抽象的な概念を説明する際には、CGの方が理解度が高まりやすく、営業やプレゼンテーションの場面でも役立つでしょう。
社内のリソース確保に貢献
外注することで、社内の人員や設備を大きく割かずに済みます。撮影準備やセット制作といったコストも不要になり、限られた予算を効果的に活用できます。
また、自社スタッフは本来の業務に集中できるため、全体のリソース配分を最適化できる点もメリットです。
さらに、専門家に任せることで制作スピードが安定し、スケジュール全体の見通しも立てやすくなります。
結果的に、プロジェクト全体の効率化や品質向上につながるのです。
CGを外注する際の注意点やデメリット
外注には多くのメリットがありますが、依頼前に理解しておきたい注意点やデメリットも存在します。ここでは代表的な2つを取り上げます。
時間がかかる可能性も
CG制作は複数の工程を経て完成するため、想像以上に時間を要する場合があります。モデリング、アニメーション、レンダリングといった作業はそれぞれ専門性が高く、1つの工程に数日から数週間かかることも珍しくありません。
特に細部までリアルさを追求する場合や、複数の修正が重なると納期が延びやすくなります。
急ぎの案件であれば、事前にスケジュールに余裕を持つか、短納期対応が可能な外注先を選ぶ必要があります。
予算によってできることが限られる
CG制作は、表現の幅が広い一方でコストとの兼ね合いが大きな課題になります。シンプルなモーションであれば比較的安価に済みますが、キャラクターの精緻な動きや映画のようなリアルな質感を追求すると、費用は一気に膨らみます。
予算が限られている場合は、シーン数を減らす、尺を短くするなど、工夫をしなければ希望通りの表現は難しいでしょう。
また、見積もりには含まれていない追加費用が発生する可能性もあるため、契約前に「どこまでが依頼範囲か」を明確にしておくことが重要です。
CGの依頼先の種類と特徴
CG制作を依頼する場合、どこに頼むかによって成果物の質やコスト、進め方が大きく変わります。代表的な依頼先は「制作会社」「フリーランス」「クラウドソーシング」の3つです。
それぞれの特徴を把握して、自分の目的に合う選択肢を考えてみましょう。
CG制作会社
制作会社は、社内に複数の専門スタッフを抱えているため、安定した品質と幅広い対応力が魅力です。モデリング、アニメーション、エフェクトなどを分業体制で進められるため、大規模なプロジェクトや短納期の案件にも柔軟に対応できます。
また、ディレクターが窓口となって進行管理をしてくれることが多く、依頼側は全体を任せやすいのも利点です。
一方で、費用は3つの依頼先の中でも高めになりやすく、予算に余裕がないと選びにくい面があります。
フリーランス
フリーランスに依頼する場合は、個人のスキルや経験に直結した成果物が得られる点がメリットです。費用も制作会社に比べて抑えられるケースが多く、柔軟なやり取りができるのも魅力でしょう。
小規模な案件や特定分野に特化した制作をしたい場合には向いています。ただし、クオリティにばらつきがあるため、ポートフォリオや実績の確認は欠かせません。
さらに、1人で対応する分、スケジュールが詰まると納期が延びたり、大規模案件への対応が難しかったりする点には注意が必要です。
クラウドソーシング
クラウドソーシングサービスを利用すると、短期間で多くの候補者から提案を受けられます。候補者の中には、フリーランスはもちろん、会社自体がクラウドソーシングサービスに登録している場合もあります。
小規模で低予算の案件でも発注しやすく、初めてCGを試したい場合の入り口としても使いやすい仕組みです。コストを抑えつつ、気軽に依頼できるのが大きなメリットです。
ただし、依頼先によってスキルや経験の差が大きく、品質や納期の管理が難しくなることもあります。また、著作権や利用範囲などはクラウドソーシングサービス側の規約も確認が必要です。
失敗しない外注先の選び方
CG制作を外注する際、どの依頼先を選ぶかで成果は大きく変わります。費用やスケジュールだけでなく、完成後の満足度にも関わるため、外注先の選び方の基準を押さえておくことが大切です。
以下の4つは最低限チェックしておきたいポイントです。
ポートフォリオや制作実績の確認
依頼先の得意分野や表現力を知るには、過去の作品を確認するのが最も確実です。
実力のある外注先でも、「アニメ調は得意だけどリアリティの方は苦手…」など、得手不得手があります。自分が作りたいイメージに近い実績があるかどうか、テイストやクオリティに一貫性があるかを見極めましょう。
複数の候補を比較すれば、力量の差も見えてきます。実績紹介の中で「どの部分を担当したのか」まで聞けると、より判断がしやすくなります。
見積もり内訳と追加費用の確認
提示された金額が何に基づいているかを理解することは、トラブルを避ける上で重要です。モデリング、アニメーション、編集などの工程ごとに費用が分かれているか、どの範囲までが含まれているかを確認しましょう。
さらに、修正回数や特殊効果の追加といった条件で追加費用が発生するのかどうかも要チェックです。不明点があれば契約前に必ず質問しておくことが安心につながります。
著作権や二次利用条項の明確化
CG制作物は完成後の使い方に大きな価値があります。そのため、納品後にどの範囲で利用できるのか、二次利用は可能なのかといった点を契約段階で明確にしておきましょう。
外注先によっては著作権を完全に譲渡する場合と、利用許諾のみを与える場合があるため、想定している活用方法に合致する契約形態を選ぶことが必要です。
後々のトラブルを避けるためにも、権利関係は事前にすり合わせておきましょう。
連絡手段や進行管理ツールの確認
制作をスムーズに進めるには、外注先とのやり取りがしやすいかどうかも重要です。
レスポンスの早さや丁寧さに加え、チャットツールやプロジェクト管理ツールを利用できるかどうかを確認しておくと安心です。
定期的に進捗を共有してくれる仕組みがあるか、修正指示をどのようにやり取りするかを把握しておけば、認識の食い違いを防ぎやすくなります。
コミュニケーションの取りやすさは、完成度だけでなく納期の安定にも直結します。
【価格別】CG動画制作費用の相場
CG制作の費用は、内容や表現方法によって大きく変動します。ここでは予算ごとに一般的な目安を紹介します。
実際の見積もりは案件次第で変わるため、あくまで参考としてご覧ください。
10万円未満の場合
10万円未満の場合だと、CG動画全体を外注するのは難しく、数秒程度の短いアニメーションや簡易的なエフェクトの追加、オブジェクトのモデリングが中心になります。
例えば、ロゴの立体化やシンプルなモーション演出などです。低コストで依頼できる分、クオリティや表現の幅は限定的になります。
10万円〜30万円の場合
10〜30万円の範囲であれば、短尺のCG動画や製品のシンプルな紹介映像を依頼できるケースが増えます。例えば、10〜20秒ほどのモーショングラフィックスや製品の形状を見せる簡易的な3D表現などが可能です。
コストを抑えながらも、広告やプレゼンで活用できる映像を作りたいときに向いています。
30万円〜60万円の場合
30〜60万円の範囲では、1分前後の映像制作や、ある程度作り込んだ3DCGの表現が期待できます。プロモーション用のサービス紹介映像や展示会用の映像などに活用されるケースが多い価格帯です。
カット数や演出に工夫を取り入れる余裕があり、見ごたえのある映像に仕上げられる可能性が高まります。
60万円〜100万円の場合
60〜100万円ぐらいの予算規模になると、複数カットを組み合わせた本格的なプロモーション映像を制作できます。キャラクターアニメーションや、よりリアルな質感表現も可能です。
企業PR動画や製品コンセプトムービーなど、視聴者に強い印象を与える映像を作りたい場合に適したレンジと言えます。
100万円以上の場合
100万円を超えると、テレビCMクラスのクオリティや長尺のフル3DCG映像も範囲に入ります。大規模なチームで分業しながら制作するケースも多く、細部にまでこだわった表現が可能です。
高額にはなりますが、映像の完成度や演出の自由度は大幅に高まり、ブランド全体の価値を高めるような作品に仕上げることもできます。
価格を抑えるためのポイント
CG制作は高額になりやすいですが、発注の工夫次第で費用をコントロールできます。ここでは外注を検討している方が取り入れやすい具体的な方法を紹介します。
CG制作の尺を調整する
映像の長さは制作費に大きく影響します。1分の映像と30秒の映像では、必要なモデリング数やカット数、レンダリング時間が大きく変わるため、工数も比例して増えます。
もし訴求ポイントが複数ある場合は、すべてを1本の長尺にまとめるより、30秒程度の短い動画を複数本に分けて制作する方が、結果的に安価で効果的になることもあります。
他にも「静止画+軽いモーション」を組み合わせることで、同じ尺でもCGを使わずに見ごたえを保ち、コストを抑える工夫などもあります。
求めているクオリティを明確化する
CGの「リアルさ」は、工数に直結します。たとえば製品紹介なら、金属の質感や光沢をフォトリアルに表現するのか、シンプルなマット調で見せるのかによって、必要なテクスチャ作業やレンダリング負荷は大きく変わります。
依頼時に「どの程度のリアルさが必要か」を決めておくと、制作側も工数を見積もりやすくなり、無駄な作業を減らせます。
イメージに近い写真や既存の映像を参考資料として提示すれば、やり取りの効率も高まり、修正回数の削減にもつながります。
短納期にするか納期に余裕を持つか
スケジュールも価格を左右する一因です。短納期で進める場合、制作会社は人員を増やしたり、レンダリングマシンを追加で稼働させたりする必要があるため、割増料金が発生しやすくなります。
逆に、余裕を持ったスケジュールで依頼できれば通常工数で進行でき、追加費用がかからないだけでなく、品質面でも安定しやすいのが実情です。
「いつまでに必要か」を先に明確にし、可能なら2〜3週間のバッファを取ることで、コストを抑えながら安心感のある進行が可能になります。
制作のために必要な素材の用意
外注先が一からデータを作るほど費用は膨らみます。そのため、依頼側で用意できる素材はなるべく揃えて渡すのが賢い方法です。
製品のCADデータや図面、参考となる写真、企業ロゴやフォントデータなどがあれば、それだけでモデリングやデザイン作業の工数が減ります。
また、事前にラフスケッチや絵コンテを作っておけば、企画や演出部分にかかる時間を短縮できます。
外注先に「イメージが曖昧な状態」で丸投げすると、方向性のすり合わせに時間もコストも取られてしまうため、事前準備がコスト削減のカギになります。
修正を少なくするためのコミュニケーション
修正回数が多いほど費用は膨らみます。特にCGは1つの修正でもモデリングからレンダリングまでやり直しが必要になるケースがあり、その工数は想像以上です。
そのため、初期段階から完成イメージを細かく共有することが重要です。リファレンス映像やイメージボードを活用し、「この質感で」「この動きで」という具体的な指示を最初に伝えておくと、後の大幅修正を防げます。
さらに、制作途中でも定期的に中間チェックを行うことで、方向性がズレたまま最後まで進んでしまうリスクを避けられます。
結果的に、修正が減ればスケジュールも守られ、余計な追加費用もかかりません。
CG動画制作の流れ
実際にCGを外注すると、どのようなステップを経て映像が完成するのでしょうか。
ここでは一般的な流れを4つの段階に分けて紹介します。依頼前に全体像を知っておくことで、スケジュールや予算を検討しやすくなります。
STEP1.ヒアリング・要件定義
最初の段階は、依頼内容や目的を制作側に伝える「ヒアリング」です。どんな映像にしたいのか、ターゲットは誰か、利用シーンはどこかといった基本情報を整理し、必要な尺や納期、予算感をすり合わせます。
この段階で伝える情報が具体的であるほど、見積もり精度が高まり、後の修正リスクも減ります。参考となる映像や写真を見せながら説明すると、イメージが共有しやすいでしょう。
STEP2.企画・絵コンテ
要件をもとに、外注先が企画や構成を練り、映像の流れを可視化する「絵コンテ」を作成します。絵コンテは場面ごとのイラストやカットの説明が並んだ資料で、完成映像の設計図のようなものです。
この段階で演出や表現の方向性を固めておくことで、制作がスムーズに進みます。
加えて、BGMやナレーションの有無など、付随要素もここで決めておくと後の工数が減りやすくなります。
STEP3.CG制作
企画が固まったら、いよいよCGの実作業に入ります。
まず「モデリング」でキャラクターや背景、製品などの3Dモデルを作成し、続いて「アニメーション」で動きをつけます。必要に応じてライティングや質感設定を加え、リアリティや演出効果を高めます。
最終段階は「レンダリング」です。完成した3Dデータを映像として書き出す工程で、複雑なシーンほど時間がかかります。
レンダリングは数時間から数日単位で処理が必要になることもあり、納期を考える際にはこの工程を念頭に置く必要があります。
STEP4.修正・納品・運用サポート
一度出力した映像を依頼側が確認し、修正点があればフィードバックします。
修正はモデリングの調整からアニメーションの再設定、再レンダリングまで幅広く、追加工数につながりやすいため、契約時に「修正回数」を取り決めておくと安心です。
最終版が完成したら、希望の形式(例:MP4やMOV)で納品されます。外注先によっては、映像の使い方に合わせた運用サポートを提供する場合もあります。
例えば、展示会向けにループ再生用のデータを準備したり、SNS用に短く再編集したりする対応です。
こうしたアフターケアがあるかどうかも、外注先を選ぶ際のポイントになります。
最高のパートナーにCG制作を依頼しよう!
ここまで、CG制作を外注するメリットや注意点、費用相場、依頼の流れを紹介してきました。CGの外注は決して安くはありませんが、その分だけ大きな価値をもたらします。
一方で、予算やスケジュールに制約がある中で進めなければならないことも多いでしょう。だからこそ、依頼先を選ぶ際には「実績」「見積もりの透明性」「権利関係」「コミュニケーション体制」といったポイントを確認することが重要です。
CG制作ならTeam HENSHINへお任せください!
CG制作の外注をご検討の方は、ぜひ私たちTeam HENSHINへご相談ください。弊社では、予算に合わせて提案させていただき、実現したい内容をサポートいたします。
映画やMV、CM、YouTube、製品PVなど幅広い実績もございますので、制作実績については、下記のページもご覧ください。
そして、弊社は最新AIの活用も強みとして挙げています。実写に3Dキャラクターを置き換えるAIを使用していたり、絵コンテで複数のイメージをAIで生成するなど、AIを幅広く活用しています。
AIを活用しているからこそ、早くて安いご提案も可能ですので、気になる方はお気軽にお問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです。




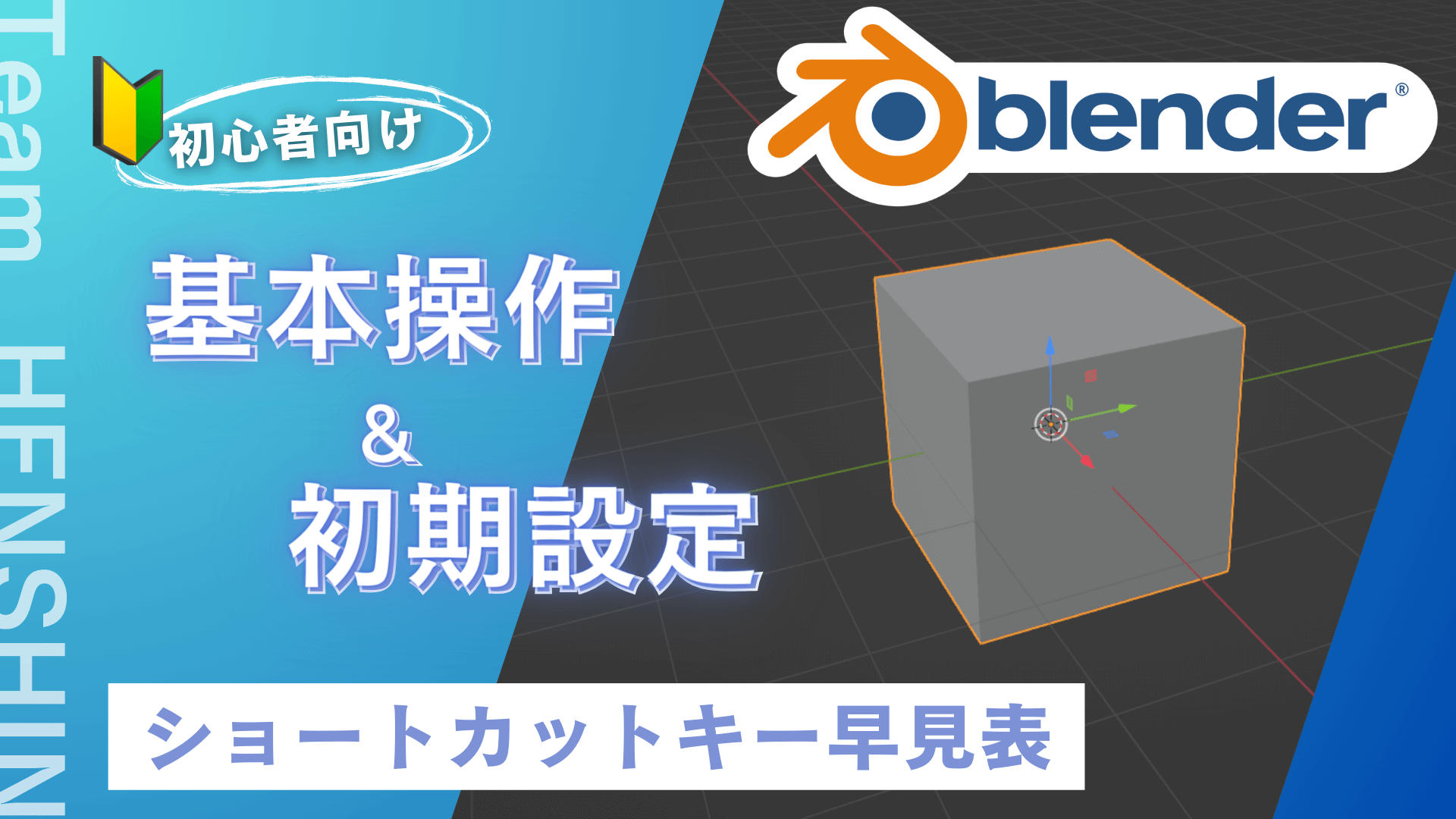

.webp)
