CGクリエイターとは?仕事内容や年収、将来性について現役クリエイターが解説!

映画やアニメ、ゲーム、さらにはメタバースのような新しい分野まで、あらゆる場面でCG表現が欠かせなくなっています。
その裏側で活躍するのが「CGクリエイター」です。専門的なソフトを使いこなし、キャラクターや世界観を形にする彼らは、映像表現の要ともいえる存在です。
しかし「CGクリエイターって具体的にどんな仕事をするの?」「なるためにどんな勉強が必要?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、仕事内容や必要なスキル、年収やキャリアパスなど、CGクリエイターを目指す人が知っておきたい情報をわかりやすく整理しました。また、現役のクリエイターにインタビューした内容も掲載しています。
これからCGの世界に挑戦したい方、あるいは業界研究をしている方にとって、進路を考えるヒントになれば幸いです。
CGクリエイターとは
CGクリエイターとは、BlenderやMayaなどの専用ソフトやツールを使ってCG(コンピュータグラフィックス)を制作する職業です。
映画・アニメ・CM・ゲームといった映像コンテンツ制作で活躍するのはもちろん、最近では建築や医療など様々な分野でCG技術が活用されており、それに伴いCGクリエイターの需要も高まっています。
CGデザイナーとの違いについて明確な定義はありませんが、一般にCGクリエイターはCG制作に関わる人全般を指す広い言葉で、CGデザイナーはその中でもデザイン分野の制作を担当する人を指すことが多い傾向です。両者は同じ意味で使われることもあります。
CGクリエイターの細かい種類

CG制作の工程ごとに、CGクリエイターにはいくつかの専門職種があります。大規模な制作会社では各工程を別々の担当者が受け持ちますが、小規模な会社やフリーランスでは一人で複数工程を担当することもあります。
代表的な職種として、以下のようなものがあります。
モデラー
モデラーは、キャラクターや建物、道具などの立体的な形状を3Dソフトで制作する職種です。
デザイン画やコンセプトをもとにポリゴンやスカルプト機能を駆使して造形し、映像やゲームの世界を支える基盤を作ります。
キャラクターの場合は関節の動きや後のリギングを意識した構造が必要で、背景であれば空間のスケール感やディテールの作り込みが重要です。高い観察力と造形力が求められるため、デッサンや立体造形の基礎が役立ちます。
作品の第一印象を決める要素でもあり、モデラーの出来栄えが全体の完成度を左右すると言っても過言ではありません。
リガー
リガーは、モデルを動かすための骨格(リグ)やコントロール機構を組み込む役割を担います。キャラクターであれば関節や筋肉の動きが自然になるよう設定し、アニメーターが扱いやすい形に整えるのが主な仕事です。
複雑なキャラクターでは表情や髪、衣服の揺れまで考慮し、破綻のない動作を可能にします。
高度なリグを作成するには、解剖学的な知識やソフトの仕組みの理解が必要です。さらに、効率化のためにスクリプトやプログラミングを活用することも多く、技術的な側面が強い職種でもあります。
リガーの作業が適切かどうかで、後工程のスムーズさが大きく変わります。
アニメーター
アニメーターは、モデラーが作成した3Dモデルに動きを加える仕事です。
キャラクターに歩行や走行などの基本的なモーションをつけるだけでなく、感情を伝える表情の変化や仕草も表現します。作品によっては建物が崩れるシーンや乗り物の挙動、自然現象の動きなども担当範囲に含まれます。
動きには物理法則の理解や、人間や動物の観察に基づくリアルさが求められます。一方でアニメ調やファンタジー作品では、誇張表現を駆使した創造的な演出も必要です。
人や生物の動き、物理法則への深い理解と観察眼が求められ、細かな動きの違いによる印象の差にもこだわる繊細さも重要です。
テクスチャアーティスト
テクスチャアーティストは、モデラーが作った3Dモデルに色や質感を付与する職種です。木材や金属、布、肌といった素材ごとの質感を反映させることで、モデルをリアルに見せることができます。
作業ではPhotoshopやSubstance Painterなどのツールを用い、時には一からテクスチャ素材を描き起こすこともあります。
観察力が重要で、実際の質感を正しく捉えられるかがクオリティに直結します。また、ライティングやレンダリング時に意図した見え方になるよう調整する知識も必要です。
テクスチャアーティストの技量によって、作品の説得力が大きく変わるといえます。
エフェクター
エフェクターは、爆発・炎・煙・光・水しぶきといった特殊効果をCGで生み出す職種です。作品の迫力や臨場感を高めるために欠かせない役割で、アクションシーンやファンタジー表現では特に重要です。
物理演算やパーティクルシミュレーションを活用し、リアルさと演出効果の両立を図ります。自然現象の仕組みに対する理解も必要で、例えば炎や煙の動きは現実を観察することで精度が増します。
ゲーム分野でも魔法や必殺技の演出などに用いられ、ユーザー体験を大きく左右する要素です。
華やかに見えますが、処理負荷を考えたデータ設計など地道な技術的工夫も求められる仕事です。
コンポジター
コンポジターは、モデリングやアニメーション、エフェクトなど様々な要素を合成し、最終的な映像に仕上げる工程を担当します。CGだけでなく、実写映像や背景画など複数の素材を組み合わせて違和感のない映像を作り上げます。
作業では色調補正や明暗の調整、不要な要素の除去なども行い、全体を統一感のある画面に整えます。映像の完成度を左右するポジションであり、細かな部分まで気を配る注意力が求められます。
コンポジターは制作の最終段階を担うため、責任が大きい分やりがいも大きい職種です。
業界別のの仕事内容

CGクリエイターが活躍するフィールドは多岐にわたります。ここでは代表的なゲーム・映像・広告・メタバースの各業界における仕事内容の特徴を紹介します。
それぞれの業界で求められる表現や技術に違いがありますので、志望分野に応じたスキルを意識するとよいでしょう。
ゲーム業界
ゲーム業界はCGクリエイターの代表的な活躍の場で、キャラクターデザインから背景、エフェクト演出まで幅広く携わります。特にリアルタイムで動作するゲームは、見た目の美しさと同時に処理の軽さも両立しなければならないため、モデリングやテクスチャにおいて最適化の知識が重要です。
大規模タイトルでは分業化が進み、モデラーやアニメーターなど専門性の高い役割に分かれます。一方、インディーやスマホ向けゲームでは一人が複数の工程を担当することも珍しくありません。
近年はVRやARゲームの普及により、リアルタイムレンダリングやインタラクション設計のスキルを持つ人材の需要も増えています。
ゲームエンジン(UnityやUnreal Engineなど)上でリアルタイムに動作するデータを制作する必要があるため、ポリゴン数の最適化や動作検証などプログラミングに近い知識も求められます。
映像業界
映画やアニメ制作では、実写映像に合成するVFXや、背景・小物を3DCGで表現する作業が主流です。
たとえば怪獣映画では怪物そのものをCGで作り、実写映像と融合させることで迫力ある映像表現を実現します。アニメでは背景やメカなどをCG化し、作画との調和を図ることも一般的になっています。
映像業界のCG制作はリアリティを重視する場面が多く、質感やライティング調整へのこだわりが強く求められます。
大規模プロジェクトでは数十人単位のチームで分業され、コンポジターやエフェクトアーティストなど専門的な職種が活躍します。国際的な作品に関わるチャンスもあり、スキル次第で世界的に評価される可能性のある領域です。
広告業界
広告では短い尺の中で商品やサービスの魅力を伝えるため、インパクトのあるCG表現が多用されます。
自動車のCMでは実写では難しい疾走シーンをCGで描き、化粧品広告では成分のイメージを抽象的なビジュアルで演出するなど、発想力が試される分野です。
限られた納期の中で高品質なビジュアルを仕上げる必要があり、スピード感のある制作体制が重視されます。
近年はWeb動画やSNS広告の需要が高まり、短期間で多種多様なバリエーションを作れる柔軟性も必要です。
広告分野は映像表現の自由度が高く、CGクリエイターの創造力が直接クライアントのメッセージに影響を与えるやりがいの大きい仕事です。
メタバース業界
メタバース領域はまだ新しい分野ですが、仮想空間の基盤をつくるCGクリエイターの役割は非常に大きいです。アバターのデザインや仮想都市の建築物、インタラクティブに動作するアイテムなど、ユーザーが体験するすべてがCGによって構築されます。
ゲーム業界と同じく、ゲームエンジンの知識も必須になり、ユーザーが自由に視点を動かし行動できるため、全方向から見られるモデルや軽量化されたデータが必要です。
VRイベントやバーチャルライブの開催が増える中で、没入感を高めるための空間演出やリアルタイム表現を扱える人材は特に重宝されています。
今後さらに成長する可能性が高い領域であり、最新技術に敏感なクリエイターにとっては挑戦しがいのある舞台です。
CGクリエイターの平均年収と需要の推移
CGクリエイターの収入は、経験年数や役割によって大きく変わります。以下はあくまで目安ですが、年代ごとに整理すると理解しやすいでしょう。
年代別の年収イメージ
- 20代前半(新人)
- 300万〜400万円前後
- アシスタント的な業務が多く、下積みの時期
- 20代後半〜30代
- 400万〜600万円
- 実務経験が評価され、リーダー職や専門性のある職種を任されやすい
- 40代以降
- 500万〜800万円以上
- 管理職やフリーランスとして働く人も多く、実力次第で大幅な収入増も可能
一方で、国内のCG業界全体の給与水準はITエンジニアなどに比べると低めとの指摘もあります。とはいえ、専門性を高めれば待遇改善につながるケースも多く、スキルアップが年収アップの鍵になります。
需要の広がり
- エンタメ分野:ゲーム、アニメ、映画での需要は今も高水準。特にスマホゲームや配信向け作品の増加が顕著。
- 産業分野:建築パースや製造業のシミュレーション、医療分野での可視化など、非エンタメ領域でも活用が拡大。
- 新技術分野:メタバース、VR/AR、生成AIとの組み合わせは今後の成長が期待される。
CGというと映画やゲームなどのエンタメ分野が真っ先に思い浮かびますが、様々な分野へ仕事の幅が広がりつつあります。新しい技術に対応できる人材は、今後さらに需要が高まるといえるでしょう。
CGクリエイターに向いている人とは
やりがいのあるCGクリエイターという仕事ですが、どのような人が向いているのでしょうか。ここでは、向いている人と向いていない人の特徴について紹介しています。
向いている人の特徴
CGクリエイターに向いている人には、以下のような共通点があります。
- 細かい作業に集中できる
- 3Dモデルやテクスチャ制作は、数時間単位で地道な調整を行う場面が多いため、集中力と忍耐力が重要です。
- 観察力がある
- 人や物の形、動き、質感を的確にとらえられる人は、リアルで説得力のある作品を作りやすいです。
- 新しい技術に興味を持てる
- 業界は進歩が早く、ソフトやツールは数年で更新されます。学び続ける姿勢がある人ほど長く活躍できます。
- チームワークを大切にできる
- 大規模な制作では分業が当たり前。周囲との意思疎通や協力が欠かせません。
- 作品やエンタメが好き
- ゲームや映画への強い興味がある人は、困難な場面でもモチベーションを保ちやすいです。
向いていない人の特徴
一方で、次のような傾向が強い人は仕事の中で苦労しやすいかもしれません。
- 単調な作業がすぐに飽きてしまう
- CG制作は微調整や繰り返し作業の連続です。短気な性格だと辛く感じやすいです。
- 技術の勉強を避けたい
- 常に新しいソフトや手法を学ぶ必要があるため、学習意欲が低いと成長が止まってしまいます。
- 他人とのコミュニケーションが極端に苦手
- 完全に一人で完結する仕事ではないため、報告や相談を避ける人は現場で孤立しやすいです。
- 作品のクオリティにこだわりを持てない
- 「これくらいでいい」と妥協してしまう姿勢だと、求められる水準に達しづらいです。
- 映像やゲームに興味が薄い
- 成果物に関心がないと、厳しい環境を乗り越えるだけのモチベーションを維持するのは難しくなります。
CGクリエイターになるための方法
CGクリエイターを目指すルートはいくつか存在します。もっとも一般的なのは専門学校や大学で学ぶ進路ですが、独学や職業訓練校を利用してスキルを身につける人も少なくありません。
ここではCGクリエイターになるための代表的な4つの方法を紹介します。
専門学校に通う
CGや映像制作に特化した専門学校では、業界標準のソフト操作や作品制作を実践的に学ぶことができます。2〜3年という短期間で必要なスキルを集中的に身につけられるのが特徴です。
多くの学校では就職サポートや企業との連携授業も行われており、在学中にポートフォリオを整えて就職活動に備えることが可能です。
学費はかかりますが、効率よく業界に近づける選択肢といえます。
CGが学べる大学に通う
大学では美術系や工学系を中心に、CGを学べる学部や学科が存在します。専門学校に比べて4年間と時間はかかりますが、幅広い知識を学べる点が大きな特徴です。
デザインや情報処理の基礎から、研究や理論的なアプローチまで取り組めるため、表現力だけでなく企画力や分析力も磨けます。
卒業後には学位を得られるため、進路の選択肢を広く持てることも強みです。
ここでTeam HENSHINのメンバーである加藤の例を紹介します。
担当業務や仕事内容は?
基本的にモデラー/リガー/アニメーター/テクスチャアーティスト/エフェクター/コンポジターの全ての仕事を行っていて、案件によって立場が変わります。
プロジェクトマネージャーやクリエイターの進捗管理などを行うディレクターを担当することもあります。
どうやってCGのスキルを勉強した?
自分の作りたい作品に合わせてチュートリアルを探す、好きなMVや映画のシーンを模倣する、海外の技術をリサーチし応用するなど、表現手法を増やすことを繰り返して学んでいきました。
美大に進学して、授業として様々なことを学びましたが、授業外で自主的な技術研鑽を行っていました。
初心者やこれから志す人へのアドバイスを!
やりたい表現がある方が勉強が捗ります。「CGができるようになりたい」ではなく、「こういう表現をしたい」があると良いです。そのためにCGを学ぶ…という形の方が生きてくると思います。
自分の強みを活かせる方向に合わせて技術を磨くことで、そこに様々なスキルも付随して得ることができます。とにかく手を動かしてみましょう!

独学で勉強する
市販の教材やオンライン講座を活用すれば、独学でCGを学ぶことも可能です。近年は無料で使えるソフトや動画チュートリアルが充実しており、環境としては恵まれています。
Team HENSHINでもCGクリエイターに役立つノウハウを本メディアやYouTubeで発信しています。気になる方はぜひご覧ください。
自分のペースで進められる一方で、客観的な評価を受けにくく、モチベーションを保つ工夫が必要です。学習を継続できれば、作品を発表しながら実績を積み重ねていくこともできるでしょう。
ここでTeam HENSHINの代表である村上の例を紹介します。
担当業務や仕事内容は?
実写合成が多く、アニメーター/テクスチャアーティスト/エフェクター/コンポジターの業務を行うことが多いです。
最近ではAIの進化が目まぐるしく、様々なAIを勉強して会社の技術力向上に努めています。AIの技術をCG制作に取り入れたり、AIだけで動画を作ったりもしています。
あとは、代表としてプロジェクトマネージャーや営業として活動することも多いです。
Team HENSHINは少数精鋭のチームなので、個人が幅広い業務を行うことが多いです。会社やチーム、プロジェクト自体の規模によって担当業務は変わって来やすいですね。
どうやってCGのスキルを勉強した?
海外チュートリアルを1日少なくとも2つほど…毎日4時間程度は勉強しました。CGの全体像が少し見えてきたのが、チュートリアルを100本ぐらいこなした時だったので、200時間は勉強しました。
そこから仕事にしていくために、さらに400時間ぐらいをかけて勉強しました。
実際に私が勉強したチュートリアルはVideo copilotのAfter Effectsのチュートリアルと、CG ShortcutsのCinema 4Dのチュートリアルをメインに勉強しました。
今は様々なチュートリアルが発信されているので、国内外からたくさん勉強すると良いですね。
Team HENSHINでも記事や動画で発信しているので、ぜひお役立てください!
初心者やこれから志す人へのアドバイスを!
アーティストではなく仕事でCGをやりたい場合、必要なのはセンスよりも学習能力だと思います。
新しいツールや技術を学ぶ心構えと、お客様とのコミュニケーションの仕方、提案力等のかけ算で総合力が求められる仕事になります。
ぜひ自分の可能性を信じて頑張ってください!
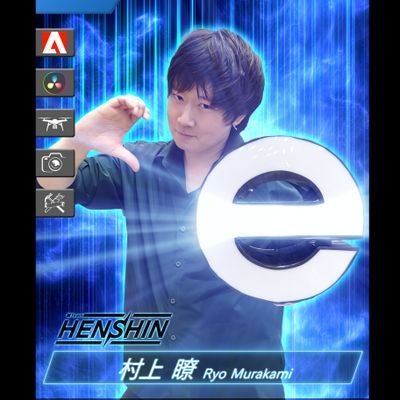
職業訓練校で学ぶ
職業訓練校は、転職や再就職を目的とした教育機関で、短期間でCGの基礎を学べるコースが用意されています。受講料が安価または無料の場合もあり、社会人が学び直しをする場として利用されることが多いです。
基礎中心のカリキュラムですが、ポートフォリオ作成や就職支援を受けながら新しいキャリアを築くきっかけになります。特に30代以降で異業種から挑戦する人にとって、有効な選択肢の一つとなっています。
CGクリエイターに必要なスキル
CGクリエイターは、専門的な技術力と人間的なスキルの両方が求められる職業です。映像やゲームの表現力を高めるには、モデリングやアニメーションといったハードスキルが欠かせません。一方で、チームで仕事を進める以上、周囲との協力や課題解決力も同じくらい重要です。
さらに近年は生成AIなど新しい技術が現場に導入されつつあり、それをどう活用するかも大きなテーマになっています。
ここでは必要とされるスキルを整理して紹介します。
必須となるハードスキル
CGクリエイターとして現場で通用するためには、基盤となる技術が欠かせません。
冒頭で紹介した仕事内容と重複するので、簡潔に紹介します。なお、それぞれを専門職とする場合もあるので、必ずしも全てのスキルが必要というわけではありません。
モデリング
キャラクターや背景などの形状を立体的に作り出すスキルです。正確な造形力に加え、後工程でアニメーションがしやすい設計を意識する必要があります。
観察力とデッサン力が基礎にあると、より完成度の高いモデル制作が可能です。
リギング
モデルに骨格や制御用の仕組みを設定し、動かせるようにする技術です。キャラクターの関節や表情が自然に動くように調整するため、テクニカルな理解が求められます。場合によってはプログラミングを用いて効率化を行うこともあります。
アニメーション
作成したモデルに動きをつけるスキルです。歩行や表情などの基本的な動作から、戦闘シーンや自然現象の演出まで幅広く対応します。リアリティを出すためには物理法則や人体の動きを理解することが不可欠です。
ゲームエンジンの理解
UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンは、ゲームやVRの開発に必須のツールです。モデルやモーションを組み込み、リアルタイムに動作させる仕組みを理解しておくことで、制作の幅が広がります。
特にゲーム業界やメタバース分野を目指す場合は欠かせないスキルです。
人的なソフトスキル
高度なCG技術を持っていても、チーム制作の現場では人との関わり方が成果を左右します。ここでは現場で特に重視される3つのソフトスキルを紹介します。
コミュニケーション能力
CG制作は分業が基本で、モデラー、アニメーター、コンポジターなど多様な職種が協力して一つの作品を作り上げます。そのため、自分の進捗や問題点を分かりやすく共有できる力が不可欠です。
また、クライアントやディレクターに制作意図を伝える機会も多く、専門用語をかみ砕いて説明するスキルも求められます。
円滑なコミュニケーションは、手戻りを防ぎ、チーム全体の効率を高める要素になります。
プロジェクト管理力
CGの現場では、短納期で膨大な作業をこなすことが少なくありません。そのため、タスクを整理し、優先順位をつけながらスケジュール通りに進める力が重要です。
個人レベルでは自己管理が中心ですが、経験を積むとチームリーダーとして他メンバーの進捗を把握し、全体を調整する役割も担うことになります。
納期を守りつつ高いクオリティを実現するには、計画性と柔軟な調整力の両立が欠かせません。
問題解決力
制作過程では、想定外のトラブルや表現上の課題が必ず発生します。その際にトラブルへ冷静に向き合い、原因を探して最適な解決策を導き出す力が求められます。
また、一人で抱え込まず、必要に応じて他のメンバーや外部の情報を活用する姿勢も大切です。問題を迅速に解決できる人材は、チームから高い信頼を得ることができます。
AI時代に必須となる生成AIの活用術
近年、テキストや画像から3Dモデルやテクスチャを自動生成するAIツールが急速に普及しています。これらは試作モデルやコンセプト案を短時間で出力できるため、従来は数日かかっていた作業を数時間で完了させることも可能になりました。
ただし、AIが出力する結果は必ずしもそのまま実務に使えるとは限りません。形状の破綻やテクスチャの不自然さなどを修正する必要があり、最終的なクオリティを判断するのは人間の役割です。そのため、AIを「代替手段」としてではなく「効率化の補助」として使いこなす姿勢が求められます。
Team HENSHINでも、実際に制作でAIを活用する場面は多々あります。生成AIをうまく取り入れられるCGクリエイターこそ、今後の制作現場で必要とされる存在になるでしょう。
CGクリエイターのキャリアパス
CGクリエイターとしてスキルを身につけた後は、どのような働き方を選ぶかによってキャリアの方向性が変わります。ここでは代表的な3つのキャリアパスを紹介します。
制作会社に勤める
もっとも一般的なキャリアは、ゲーム会社や映像制作会社などの制作現場に就職する道です。新人時代は先輩の補助作業から始まり、徐々に主要なパートを任されるようになります。
会社勤めは安定した収入を得やすく、チーム制作を通して多くの経験を積めるのが強みです。その一方で、納期に追われる環境や案件を自由に選べない点は覚悟しておく必要があります。
フリーランスで業務委託を受ける
実務経験を積んだ後、フリーランスとして独立する道もあります。特定の工程に強みを持っていれば、専門性を生かして案件単位で収入を得られます。
働く時間や場所を自分で決められる自由度が魅力ですが、案件が途切れるリスクや営業・契約処理といった業務も自分で行わなければなりません。
安定よりも裁量や挑戦を重視したい人に合った働き方です。
自身の活動で生計を立てる
近年は、個人制作のゲームや映像を配信・販売して収益化するクリエイターも増えています。アセット販売やYouTubeなどを活用して、自分の作品を直接ユーザーに届ける形です。
成功すれば大きな収入源になりますが、軌道に乗るまでは収益が安定しにくいのが現実です。ビジネス的な発想やセルフプロデュース力が求められるため、純粋な制作力に加えてマーケティング視点も欠かせません。
CGクリエイターに関するよくある質問
ここでは、CGクリエイターを志す方からよく聞く質問とその回答をまとめています。
CGクリエイターで仕事をするために資格は必要?
CGクリエイターとして働くために必須の資格はありません。採用や案件獲得の際に重視されるのは、資格よりもポートフォリオや実務経験です。
プログラミングのスキルは必要?
必ずしも全員に求められるわけではありません。モデリングやアニメーションを中心とする職種では不要なことが多いですが、リギングやツール開発に関わる場合はPythonなどの知識があると強みになります。
30 代・40 代からでも目指せる?
年齢に関係なくCGクリエイターを目指すことは可能です。異業種からの転職事例もあり、社会人経験があることでマネジメントやコミュニケーション力を評価されるケースもあります。
ただしスキル習得には時間がかかるため、早めに学習を始め、ポートフォリオを整えて挑戦することが重要です。
CGクリエイターを目指すか考えよう
CGクリエイターは、映像やゲームの表現を支える重要な職業です。モデリングやアニメーションといった専門技術に加え、チームで成果を出すためのソフトスキルや最新のAI技術への対応力も求められます。決して楽な道ではありませんが、自分の手で世界を形にできる大きなやりがいがある仕事です。
「好きだから挑戦したい」という気持ちを持てるなら、年齢や経歴に関係なく一歩を踏み出す価値があります。進路の選択肢は専門学校・大学・独学・職業訓練校とさまざまなので、自分に合った方法でスキルを身につけていくことが大切です。
Team HENSHINは、未来のCGクリエイターにとって為になる情報発信をしています。制作に役立つ記事や動画も発信しているのでぜひご覧ください。
また現在、CGクリエイターを育成するサービスも準備中です。いずれご紹介できればとは思いますが、今すぐにでも気になるという方は、お問い合わせよりご連絡ください。


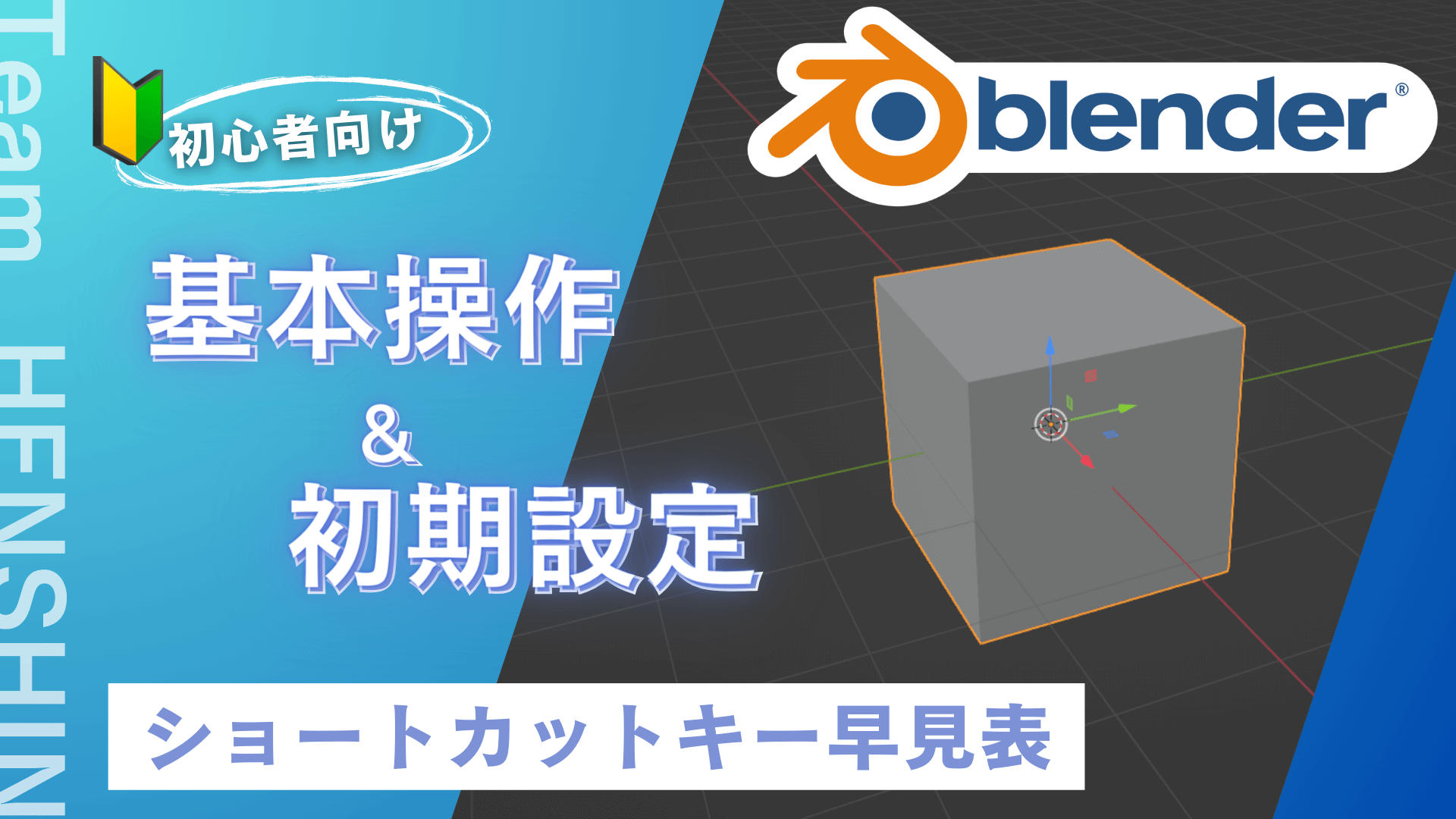
.webp)



